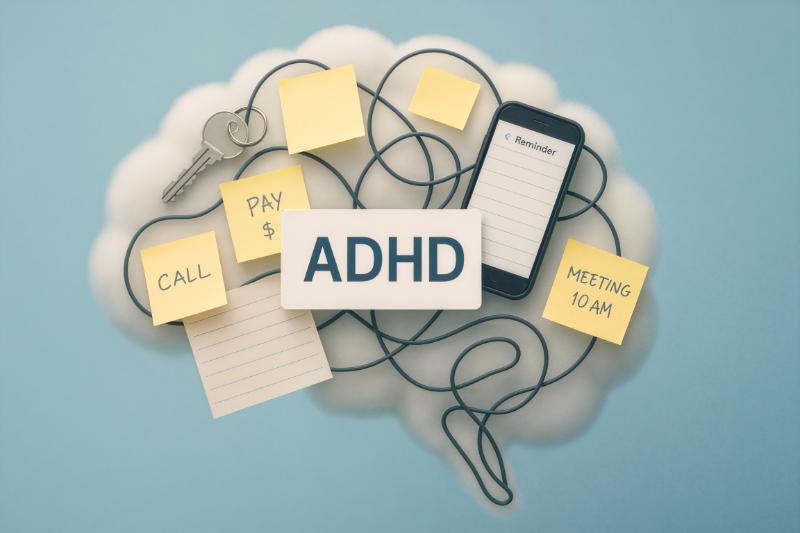大人のADHD診断とは?診断テスト・セルフチェック・診断後の行動まで徹底解説
近年、大人になってからADHD(注意欠如・多動症)の診断を受ける人が増えています。子どもの頃には気づかれずに過ごしてきたものの、社会人になって仕事や人間関係で困難を抱え、初めてADHDの可能性を意識するケースも少なくありません。
診断を受けることで、自分の特性を理解し、適切な治療や支援を受けられるようになります。
本記事では、大人のADHD診断に焦点を当て、セルフチェックの方法や診断テスト、診断の流れ、さらに診断後に行うべきことまでを詳しく解説します。
ADHDとは?
ADHD(注意欠如・多動症)は、注意力の持続が難しい「不注意」、落ち着きがない「多動性」、衝動的に行動してしまう「衝動性」などを主な特徴とする発達障害の一つです。子どもの頃に診断されることが多い一方で、大人になるまで気づかれず、社会に出てから仕事や人間関係で困難を抱えて初めて受診につながるケースもあります。
大人のADHDでは、会議での集中力不足や書類の提出忘れ、衝動的な発言など、生活やキャリアに直接影響が出やすいことが特徴です。そのため診断を受けることは、本人が自分の特性を理解し、周囲の協力を得ながらより良い生活環境を整える第一歩になります。
ADHDの症状や特徴についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてください。
『ADHD症状あるある!ADHDの種類や特徴・コントロール法』
『ADHDの治療薬。服用前に知っておきたい効果と副作用とは』
『ADHDの特徴とは?大人と子どもの違いやチェック方法、治療法まで解説』
大人向け|ADHDの診断テスト

ADHDは子どもの頃に診断されるイメージがありますが、大人になってから気づくケースも少なくありません。以下は大人のADHDに多く見られる特徴をまとめたチェック項目です。
- 約束や予定をよく忘れる
- 片付けや整理整頓が苦手で、物をなくしやすい
- 会議や授業中に集中が続かず、関係のないことを考えてしまう
- 衝動的に発言・行動してしまい後悔することがある
- 興味のあることには熱中しすぎて時間を忘れる
これらの症状について、詳しく見ていきましょう。
約束や予定をよく忘れる
スケジュール帳やアプリを使っても、約束や締め切りを忘れてしまうことが頻繁にあります。結果として、仕事上の信頼に影響したり、人間関係のトラブルにつながる場合もあります。
片付けや整理整頓が苦手で、物をなくしやすい
机の上や自宅が片付かず、必要な書類や物をすぐに見つけられないことがあります。
忘れ物が多い、持ち物を探す時間が長いといった行動は、ADHDの特徴としてよく見られます。
会議や授業中に集中が続かず、関係のないことを考えてしまう
人の話を最後まで聞くのが難しかったり、会議中に別のことを考えてしまい内容を聞き漏らすことがあります。集中力の持続が難しい点は、大人のADHDで顕著に表れる特徴です。
衝動的に発言・行動してしまい後悔することがある
思いついたことをすぐ口にしてしまい、相手を驚かせたり場の雰囲気を乱してしまうことがあります。後で「言わなければよかった」と後悔する場面が多いのもADHDに見られる傾向です。
興味のあることには熱中しすぎて時間を忘れる
好きなことや得意分野に取り組むときには強い集中力を発揮しますが、気づけば何時間も経っていることがあります。生活のリズムが乱れたり、他の大切な予定を犠牲にしてしまうことも少なくありません。
これらの傾向は誰にでも一時的に見られることはありますが、日常生活や仕事に継続的な影響を与えている場合には注意が必要です。当てはまる項目が多いと感じる場合には、専門医に相談し、ADHDの診断を受けることをおすすめします。
子ども向け|ADHDの診断テスト

ADHDは幼少期から現れることが多く、学校や家庭での生活態度に特徴が表れます。以下は子どものADHDに見られる代表的な行動パターンです。
- 授業中に落ち着いて座っていられない
- 忘れ物や宿題のやり忘れが多い
- 説明を最後まで聞かずに行動してしまう
- 順番を待つのが苦手で割り込んでしまうことがある
- 気になることがあると課題に集中できない
- 衝動的な発言でトラブルになってしまう
複数当てはまる場合には、家庭だけで判断せず、発達相談機関や医療機関での診断を検討すると安心です。
授業中に落ち着いて座っていられない
授業中に立ち歩いたり、椅子を揺らしたりして集中が続かないことがあります。教師から「落ち着きがない」と注意を受ける場面もあるでしょう。
忘れ物や宿題のやり忘れが多い
ランドセルや机の中を整理できず、教科書・ノートを忘れることが頻繁にあります。宿題をやったのに提出し忘れるなど、学習面に影響が出ることも特徴です。
説明を最後まで聞かずに行動してしまう
先生や親の指示を最後まで聞かずに動き出すため、結果的に間違えたり、再度やり直しになることがあります。衝動性の強さが影響する行動です。
順番を待つのが苦手で割り込んでしまうことがある
列に並ぶ、ゲームの順番を待つといった場面で我慢できず、割り込んでしまうことがあります。周囲の友達とのトラブルにつながる場合も少なくありません。
気になることがあると課題に集中できない
授業中でも窓の外や周りの音などに気を取られ、課題に集中できないことがあります。課題を終わらせるのに通常よりも時間がかかる傾向が見られます。
衝動的な発言でトラブルになってしまう
思ったことをすぐに口にしてしまい、友達を傷つけたり、教室の雰囲気を乱してしまうことがあります。本人に悪意はなくても、人間関係に影響するケースもあるでしょう。
これらの行動は子どもなら誰にでも見られることですが、頻度が高く日常生活や学習に支障を与えている場合には注意が必要です。気になる行動が続くときは、専門の医師や発達相談窓口に相談してみましょう。
医療機関で行うADHDの診断テスト
ADHDの診断は医師の面談や日常生活の聞き取りだけでなく、心理検査や知能検査を組み合わせて行われます。
- 成人用ADHD自己記入式スクリーニングテスト(ASRS)
- コンピュータによる注意力測定テスト(CATなど)
- 知能検査(WAISなど)
ここでは、代表的な検査方法を紹介します。
成人用ADHD自己記入式スクリーニングテスト(ASRS)
成人用ADHD自己記入式スクリーニングテスト(ASRS)は、ADHDの症状をスクリーニングするための簡易的な質問票です。このテストは、世界保健機関(WHO)とハーバード大学などが共同で開発しました。ASRSは、特に大人におけるADHDの診断を助けるために作られており、18項目の質問から成り立っています。
テストは自己記入式で、日常生活や仕事、学業における不注意や衝動性、多動性の症状について自己評価します。回答者は、各質問に対して「全く当てはまらない」から「非常によく当てはまる」までの5段階で評価します。
特に重要なのは、ASRSの「パートA」と呼ばれる6項目部分で、これはADHDを発見するために特に有効とされています。
このスクリーニングテストは、ADHDの可能性があるかどうかを素早く評価するためのツールであり、診断を確定するためには、さらに詳細な評価や医師による診察が必要です。
標準注意検査法(CAT)
標準注意検査法(CAT)は、ADHDの診断に役立つ注意力を測るテストです。コンピュータを使って、反応の速さや正確さ、注意をどれだけ続けられるかをチェックします。テストは簡単な課題がいくつか提示され、被験者はその課題に反応します。
ADHDの人は、注意を長時間維持することが難しいため、テスト中に速く反応しすぎたり、間違った反応をしたりすることがあります。CATでは、注意力の欠如や衝動性を評価し、ADHDの特徴があるかどうかを確認するのに使われます。
このテストは、他の診断方法と一緒に使われ、ADHDの診断を補助する役割を果たします。
知能検査(WAISなど)
ADHD診断の一環として、WAIS(Wechsler Adult Intelligence Scale)など標準的な知能検査を用いることがあります。これにより知的機能や情報処理の速度、遂行機能などの特性が可視化され、診断だけでなく、その後の治療や支援方針を立てるうえで役立つでしょう。
ただし、知能検査だけでADHDを診断することはできず、医師は面談や他の評価と合わせて総合的に判断を行います。
ADHD診断までの流れ
ADHDの診断は一度の受診で確定するものではなく、以下のようにいくつかのステップを経て慎重に進められます。
1. 医療機関を探して予約する
2. 初診での問診を受ける
3. 心理検査・知能検査を受ける
4. 医師による総合判断を受ける
ここでは、一般的な診断の流れを紹介します。
1. 医療機関を探して予約する
ADHDの診断を受けるには、精神科や心療内科、発達障害専門外来を受診するのが一般的です。地域によっては予約が数か月先まで埋まっていることもあるため、早めの情報収集が大切です。病院の公式サイトや口コミ、自治体の医療相談窓口を活用し、自分に合った医療機関を選びましょう。
2. 初診での問診を受ける
初診では医師との面談が行われ、現在の困りごとや日常生活での支障について具体的に尋ねられます。仕事でのミスの多さや人間関係でのトラブル、学業面での集中力不足などを整理して伝えるとスムーズです。
また、幼少期からの行動特性についても確認されることが多く、家族や関係者の意見が診断の参考になる場合もあります。
3. 心理検査・知能検査を受ける
必要に応じて、WAIS(知能検査)やCAT(注意機能検査)などの心理検査が実施されます。これらの検査では注意力、記憶力、遂行機能などを数値化して可視化できます。
ただし、検査結果だけで診断が確定するわけではなく、あくまで総合的な判断材料の一つとして扱われます。
4. 医師による総合判断を受ける
最終的には、DSM-5やICD-10といった国際的な診断基準に基づいて評価が行われます。
同時に、うつ病や不安障害など他の精神疾患や身体疾患の可能性も慎重に検討し、除外診断を経て結論が下されます。診断が確定すれば、その後の治療方針や支援策について説明を受けることになります。
ADHD診断後に行うべきこととは?
ADHDの診断を受けた後は、以下のような次のステップへ進むことが重要です。
- 治療・支援方法を検討する
- 職場・学校での配慮を申請する
- 公的支援制度を活用する
- 家族や同僚に診断内容や特性を説明する
ここでは、診断後に具体的に取り組むべきポイントを紹介します。
治療・支援方法を検討する
医師の説明を受けたうえで、自分に合った治療や支援方法を選びましょう。薬物療法では中枢神経刺激薬や非刺激薬が処方されることがあり、認知行動療法では思考や行動のパターンを見直すサポートが受けられます。
環境調整も有効で、日常生活や職場環境を工夫することで症状の負担を軽減できます。
職場・学校での配慮を申請する
診断結果を活かして、必要に応じて職場や学校に配慮を求めましょう。職場では業務量の調整や作業環境の工夫、課題の進め方の変更などが可能です。学校では試験時間の延長や座席の配置変更といった支援が行われることもあるでしょう。
これらの配慮を受けることで、能力を発揮しやすくなります。
公的支援制度を活用する
ADHDの診断を受けた場合、精神障害者保健福祉手帳の取得や医療費助成制度を利用できる可能性があります。
また、就労移行支援や障害者雇用枠を活用することで、働き方の選択肢を広げることができます。公的支援を取り入れることで、生活や就労の安定につながります。
家族や同僚に診断内容や特性を説明する
診断を受けたことを家族や職場の同僚に伝えることも大切です。特性を理解してもらうことで、誤解や偏見を防ぎ、必要なサポートを受けやすくなるでしょう。
家庭や職場で協力的な環境を整えることは、治療や日常生活の安定に大きく役立ちます。
ADHDの診断でお悩みの方はみつだクリニックにご相談ください

ADHDの診断を受けることは、自分の特性を理解し、より良い生活を築くための大切な一歩です。しかし「どの医療機関に相談すればいいのかわからない」「診断後の支援まで見据えて相談したい」という不安を抱える方も多いでしょう。
みつだクリニック では、精神科・心療内科の専門医が丁寧なカウンセリングを行い、診断から治療、生活面でのサポートまでをトータルでご案内しています。
予約から診断、診断後のフォロー体制まで安心して相談いただけますので、ADHDに関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
まとめ
ADHDの診断は、セルフチェックや心理検査を経て、医師による総合判断によって行われます。大人になってから気づくケースも多く、診断を受けることで治療や支援制度、職場や学校での配慮を受けやすくなります。
「集中力が続かない」「忘れ物や衝動的な行動が多い」といった特徴が生活や仕事に支障をきたしている場合は、自己判断で終わらせず、専門の医療機関に相談することが大切です。診断を受けた後は治療や支援方法を検討し、周囲と協力しながら特性に合った環境を整えていきましょう。
みつだクリニック「予約フォーム」